目次
中医学における「肝」と「胆」の深い関係
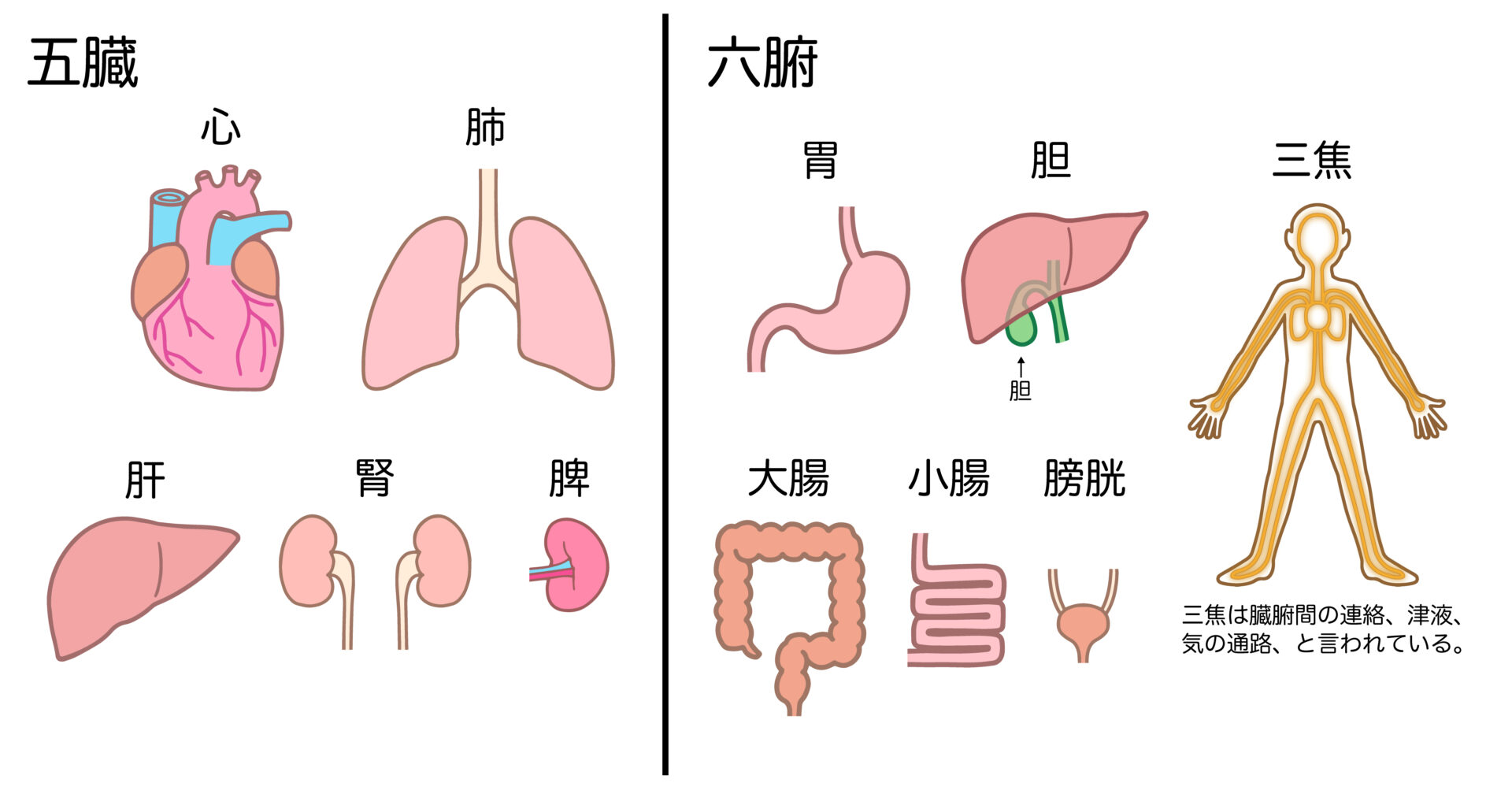
中医学では、体の中の臓器はそれぞれが独立して働くのではなく、互いに支え合い、影響し合いながら、私たちの健康を保ってい
ると考えられています。
特に重要なのが「五臓六腑(ごぞうろっぷ)」という考え方です。
五臓とは「心・肝・脾・肺・腎」、六腑とは「小腸・胆・胃・大腸・膀胱・三焦」を指します。
これらの臓腑はそれぞれペアになって機能しており、この関係を「表裏関係(ひょうりかんけい)」と呼びます。
たとえば「肝」とペアになっているのが「胆(たん)」です。肝と胆は表裏の関係にあり、まるで表と裏のように密接につながってい
て、一方の働きがもう一方に大きな影響を及ぼします。
前回は「肝」の働きについてお話ししましたので、今回はこの「肝」の相棒、「胆」についてご紹介します。
前回の内容『春と肝と目の関係』 はこちら
https://hannari-pharmacy.com/2025/03/17/yin-yang-and-the-five-elements-eyes/
『胆』の役割
「胆は決断を司る」
→ 胆は「判断力」や「決断力」と関係があり、精神の安定を保つ働きがあります。
「胆は精汁(せいじゅう=胆汁を蔵す」
→ 胆汁を蓄え、消化を助ける働きがあります。
関連する症状:
😷胆が弱ると:優柔不断、決断力が鈍る、不安感が増す
😷胆汁の流れが悪いと:消化不良、脂っこい食べ物が苦手になる
『胆が据わっている』というという言い回しがあります。
これは、「物事を恐れたり驚いたりせずに大胆になる」という意味。
反対に、胆が弱ると怖れや不安が強くなり、ビクビクした臆病な感覚が増えてくるとされてます。
例えば何かあったときに、怒られるのではないか、怒鳴られるのではないか、と不安が募り
ビクビクして心が落ち着かず、なかなか寝付けなくなってしまう・・というのは
胆の気が不足していることにより、正常な判断ができなくなってしまっていると考えます。
このような方の場合、症状としては『眠れない』という訴えになりますが、その背景には実は
胆の気虚や肝血虚が隠れていることが多いです。
胆の働きが弱っていると、胆汁酸がうまく分泌されず、脂っこいものを食べるともたれたり
下痢になったりすることも。
単に『睡眠薬』や『胃薬』を飲んでその場をやり過ごしていても、根本的な解決にはなりません。
その、背景にある原因まで想定して治療していくのが『中医学』なのです。
肝と胆の関係(肝と胆のサポート関係)
肝と胆は表裏の関係にあり、お互いの働きを支え合っています。
①肝が胆を助ける
- 肝の「疏泄(そせつ)」の働きが胆の胆汁分泌を調整
→ 肝が正常にはたらくと、胆汁の流れもスムーズになり、消化が良くなる。
→ 肝の気が滞ると、胆の働きが悪くなり、消化不良や胃もたれを起こしやすい。 - 肝が胆の「決断力」を支える
→ 肝の気が整うことで、胆の働きも正常になり、判断力が冴える。
→ 肝の気が滞ると、胆の決断力が低下し、優柔不断になったり、不安になったりする。
②胆が肝を助ける
胆の「決断力」が強いと、肝の働きも安定する
→ しっかりと決断できる人は、肝の気も安定し、ストレスが少ない。
→ 優柔不断になると、肝の気の流れも滞り、ストレスが溜まりやすい。
胆の働きが良いと、肝の気もスムーズに流れる
→ 胆が正常に機能すると、肝の気の流れが良くなり、ストレスが溜まりにくくなる。
→ 胆の働きが悪いと、肝の気が滞りやすくなり、イライラや不安感が強くなる。
このように、肝と胆は単なる臓器の組み合わせではなく、体と心のバランスを保つために、互いに支え合って働いています。
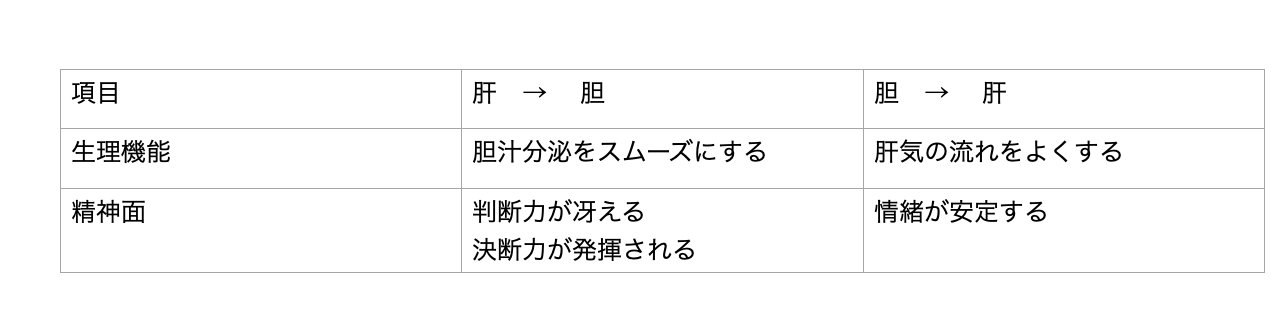
肝と胆を元気にする方法
①ストレスを溜めない
- 肝はストレスに弱いため、気分転換を大切にする。
- 軽い運動や深呼吸、趣味の時間を持つ。
②脂っこいものを控える
- 胆の働きを助けるために、油っこい食べ物やジャンクフードを控える。
- 消化を助ける大根、山芋、ウコン(ターメリック)を摂る。
③酸味のある食べ物を摂る
- レモン、酢、梅干しなどの酸味のある食べ物は肝の働きを助ける。
④睡眠の質を上げる
- 肝と胆は「夜11時~3時」に活発に働くため、この時間帯にしっかり睡眠をとる。
⑤勇気を持って決断する
- 優柔不断になりすぎず、直感を大事にして決断することで胆の働きを高める。
まとめ
- 肝は気と血を調整し、胆は決断力と消化を司る。
- 肝が胆を助け、胆が肝を支える関係にある。
- ストレスを減らし、脂っこい食事を控え、良質な睡眠を取ることで、肝と胆を元気に保てる。
肝と胆が健康だと、気の流れがスムーズになり、消化も良くなり、精神的にも安定し、決断力もアップします。
反対に、いつもは結構決めるのが早いのに、なかなか決められない、最近優柔不断気味、いろいろ思い浮かべ不安が募る・・などの精神的な症状があれば、少し肝と胆に疲れが出ているんだな・・と体を労わりましょう。
足がつりやすい、まぶたがピクピクするのは「肝」の訴え!
筋(すじ・きん)とは何か?
肝と筋には深い関係があり、肝血が筋を滋養し、緊張と弛緩をコントロールすると考えられています。
中医学でいう「筋」とは、現代医学の筋肉(筋繊維)だけでなく、腱(けん)・靭帯(じんたい)
筋膜(きんまく)などの組織も含みます。
つまり、体を動かすための全てのの組織が「肝」の影響を受けるということです。
肝の不調が筋に与える影響
① 肝血不足(かんけつぶそく) → 筋がこわばる・けいれんする
肝の血が不足すると、筋肉に十分な栄養が行き渡らず、筋が硬くなったり、けいれんを起こしやすくなります。
症状:
✅足がつる(こむら返り)
✅筋肉がピクピクと痙攣する
✅体がこわばりやすく、柔軟性が低下
✅疲れやすく、筋力が低下する
原因:
血液不足(貧血・鉄分不足)
🍙栄養不足(特にタンパク質・ビタミンB・ミネラル不足)
💤睡眠不足(夜11時~3時は肝の血を補う時間)
対策:
✔️ 肝血を補う食材を摂る(レバー、ほうれん草、クコの実、黒ゴマ)
✔️ ストレッチを習慣化(特に寝る前に軽く伸ばすと良い)
✔️ 湯船につかって血行を促進する
② 肝気滞(かんきたい) → 筋の張りや痛みが出る
ストレスや感情の乱れで肝の「気」の流れが滞ると、筋肉が緊張しやすくなります。
症状:
✅肩こりや首のこわばりがひどい
✅ストレスを感じると体がガチガチになる
✅顎関節症(食いしばり)や歯ぎしり
原因:
💢精神的ストレス(仕事・人間関係・不安など)
📱長時間の同じ姿勢(デスクワーク・スマホ)
😡怒りやイライラを溜め込む性格
対策:
✔️ リラックスする時間を作る(深呼吸、趣味、散歩)
✔️ 軽い運動で気を流す(ヨガ・ストレッチ・ウォーキング)
✔️ 酸味のある食材(梅干し・酢)で肝の気を巡らせる
③ 肝風内動(かんぷうないどう) → 手足が震える・ふらつく
肝の気や血が不足し、さらに悪化すると「風」が体内で動き、手足の震えやふらつきが起こることがあります。
症状:
✅手が震える(パーキンソン症状に似たもの)
✅めまいやふらつきが起こる
✅極端な筋のこわばりや麻痺
原因:
🩸慢性的な肝血不足
👵 老化による血の不足
🟨高血圧やストレス過多
対策:
✔️ 黒ゴマやナッツ類を摂取し、肝血を補う
✔️ 目の疲れを取る(肝と目は密接な関係)
✔️ ゆっくりした運動を取り入れる(太極拳・ストレッチ)
肝と筋を健康に保つ方法
🍚食事で肝を養う
肝血を補う食材(レバー、ほうれん草、黒ゴマ、ナッツ)
筋を強くする食材(大豆、魚、卵、鶏肉)
血行を促進する食材(生姜、シナモン、にんにくなど)
🧘♀️ ストレスを減らす
怒りやイライラを溜めない(リラックス時間を作る)
深呼吸やヨガ、散歩で気を流す
💤 睡眠をしっかり取る
子牛流中の考え方では、夜11時~3時は肝と胆の回復時間 → しっかり寝ることで筋肉の回復も促される
*「子午流中(しごるちゅう)」は、干支を使った時間の表現で1日24時間を十二支で区切って、それぞれの時間に最も
活発に働く臓腑があるという東洋医学の理論です。
この時間区分によると、午後23時〜午前3時は、肝と胆の時間となります。
👟適度な運動をする
ストレッチや軽い筋トレで筋を強化
ウォーキングや太極拳で血行を良くする
まとめ
「肝は筋を主る」= 筋肉・腱・靭帯の健康は肝の状態による!
肝血不足 → 筋がこわばる・けいれんしやすい
肝気滞 → ストレスで肩こり・筋の張りがひどくなる
肝風内動 → 震えやふらつきが起こることも(ひどい場合)
食事・運動・睡眠・ストレスケアで肝を養えば、筋も健康に!
「最近、筋肉が張りやすい」「足がよくつる」という人は、肝を整えることで症状を軽くできるかもしれません。
日常生活で気をつけるのはもちろん、症状がひどい場合には漢方薬も症状緩和に役立ちます。
当てはまるかも?と思う方はご相談ください。

